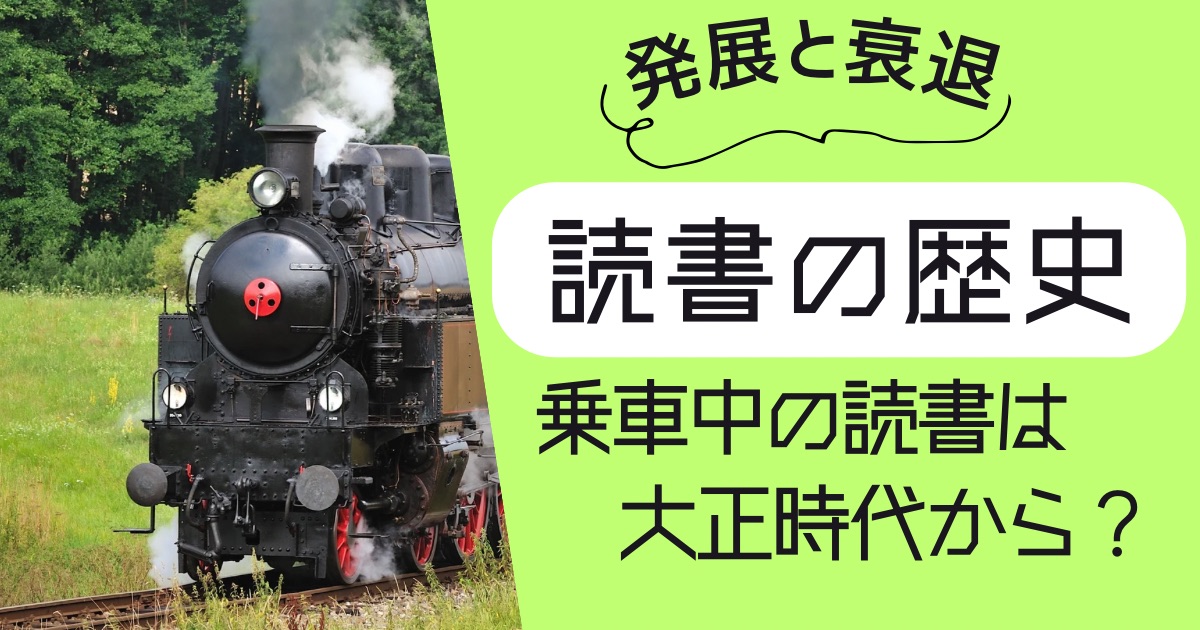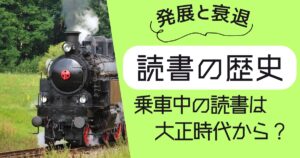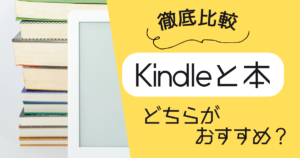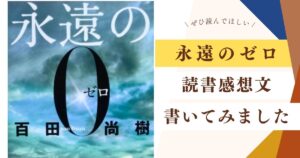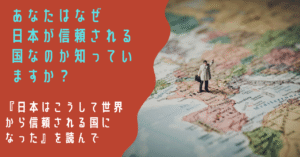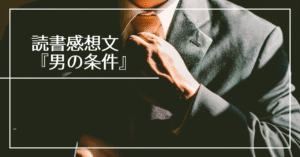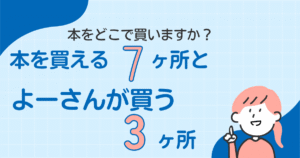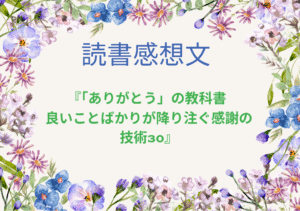Amazonのアソシエイトとして、よーさんは適格販売により収入を得ています。
 よーさん
よーさんこんにちは、よーさんです!
当ブログへお越し頂きありがとうございます。
今回は、「読書の歴史」「電車での読書の歴史」について書いていきます。
この記事を読むことで、以下のことがわかります。
- 読書の歴史
- 読書文化の発展と衰退
- 大正時代から始まった鉄道乗車中の読書の歴史
- 読書の黄金時代を作った要因
現代の読書習慣とは直接は関係ないですが、歴史を知ることで「読書」により一層興味を持ってもらえると思います。
読書習慣の参考になる話となっておりますので、ぜひ最後までご覧頂けると嬉しいです!
本題に入る前に


これまでお伝えしやすくするために、「電車」という名前で乗り物を表記しておりましたが、今回の記事では「鉄道」とお伝えします。
電車が登場する前は「機関車」が活躍しておりました。
通勤通学の時間を含めた乗車時の歴史を書くと途中からの歴史になってしまい、内容が不十分になってしまいます。
そのため、今回は電車や機関車を総称した「鉄道」の話を交えて進めていきたいと思います。
鉄道は約150年の歴史があり、長い歴史があるんですね。
明治時代からの読書の発展、鉄道と読書の繋がり


江戸時代
本を読む文化ですが、江戸時代では本は1人で読むのではなく、家族に読み聞かせ合い楽しむ「朗読(声に出して読むこと)」が主流でした。
そのため、まだ読書はされていなかったんですね。
明治時代での日本人の読書
明治時代になると、活版印刷でたくさんの本を作れるようになり、多くの人の手に渡るようになります。
また、図書館の設立したりと変化のある時代でした…..がっ!まだこの時代、日本人全体での読書率は低かったです。
理由は大きく3つあります。
1.教育の開始はしたが、識字率は発展途中
1872年の「学制」によって学校教育が始まりましたが、全国的に浸透するには時間がかかりました。特に農村部では、子どもが働き手として必要だったため、学校に通えないことも多かったです。
2.本がまだ高価だった
活版印刷の普及で本の価格は下がりましたが、それでも庶民にとってはまだ高級品でした。本よりも新聞や雑誌のほうが手に入りやすく、短い文章を読む文化が広がります。
3.読書習慣が一部の階層に限られていた
武士や知識人層は読書をする習慣がありましたが、一般庶民には「本を読む」という文化はまだ十分に定着していませんでした。ただ、新聞や雑誌の登場で、少しずつ庶民にも広がり始めます。
明治時代での鉄道内の読書
鉄道との関係性ですが、1872年(明治5年)に新橋~横浜間で日本初の鉄道が開通してます。
このころはまだ本数も少なく、乗るのは武士の子孫や富裕層、商人などの一部の人たちが中心でした。
また、車内での過ごし方は外の景色を眺めるか、会話を楽しむのが一般的で、まだ「車内で読書する」という習慣はほとんどありませんでした。
大正時代での日本人の読書
大正時代に入ると、国力向上のため識字率が下がらないよう「読書」が国で採用され、図書館が全国に増設されて読者人口が増えていきましたが、それ以外にも増えた理由があります。
1.義務教育の完全普及で識字率が大幅に向上
1910年代には、日本の識字率は90%を超えるレベルになります。学校教育が全国に広がったことで、本を読める人が圧倒的に増えていきました。
2. 本の価格が安くなり、庶民向けの本が増えた
「円本(えんぽん)」と呼ばれる、1冊1円で買える安価な本が登場して、庶民にも人気になり読書の機会が広がっていきました。これが、一般家庭における読書文化を広める大きなきっかけになります。
この円本のおかげで庶民でも名作文学に触れられるようになり、大衆文学として夏目漱石や芥川な龍之介などの近代文学が広く読まれるようになります。
大正時代での鉄道内の読書
鉄道網が発展し、通勤・通学の文化が定着したことで、移動時間が長くなっていきます。
さらに、「円本(えんぽん)」などの安価な本が普及し、読書が庶民にも広がったことで、「移動中に本を読む」という習慣が生まれました。
昭和時代での日本人の読書と、鉄道内の読書
昭和時代では、時代全体で読書率は比較的高いです。
また、1945年(昭和20年)より前までを「戦前」と言われ、戦前は年代ごとに大きく読書文化が変わりました。
戦後には教育水準の向上や出版文化の発展によって比較的高かったです。また、鉄道内や家庭での読書が一般的とされています。
特に昭和40〜50年代は「読書の黄金期」とされ、多くの人が本を読んでいました。
しかし、昭和末期から読書率が低下していきます。
昭和初期(1926年~1934年)
大正から続く読書の広がりは続きます。「円本」の流行や、新聞・雑誌の普及、探偵小説・娯楽小説の人気が特徴的な年代でした。
探偵小説では江戸川乱歩の『怪人二十面相』などが流行します。
大衆向けの娯楽小説がどんどん増えて、読書がより身近になっていきました。
昭和10年代(1935年~1944年)
この時代は、戦争の影響で自由な読書がどんどん制限されていった時期です。
1937年に日中戦争が始まり、国が「戦争を支える本しか出版できない」ように献血を強化してしまいます。
出版された本は軍国主義的な本が増加し、子ども向けには、戦争に関連する本が多く出版されました。
それまで人気だった探偵小説や純文学は影を潜め、戦争に関係する「戦時文学」が主流になります。
そして、戦争が長引くにつれて紙が不足し、本の発行部数が制限されるようになります。
そのため、新しい本がほとんど出せなくなり、読書文化そのものが縮小してしまいました。
昭和20年代(1945年~1954年)
戦争が終わると、日本の読書文化も少しずつ復活していきます。
しかし、戦後すぐは紙不足で本が少ないため、本があまり出版できませんでした。その代わりに「貸本屋」が流行し、お金がない人でも安く本を借りて読めるようになります。
また、GHQ(アメリカの占領軍)が検閲を行い、逆に戦争を美化する本は出版できなくなり、戦争中に禁止されていた「自由な思想」の本が再び出版されるようになりました。
子ども向けには、紙芝居がすごく流行し、1950年代に入ると、手塚治虫の『鉄腕アトム』など、漫画がどんどん登場し、読書のスタイルが変わっていきます。
文学作品も1947年に『近代文学』という雑誌が創刊され、戦後文学が盛り上がり、文学作品も復活をしていきました。
昭和30年代(1955年〜1964年)
戦後の復興が進み、識字率も向上しました。本や雑誌が多く出版され、文庫本の普及が始まります。
昭和40〜50年代(1965年〜1984年)
「読書の黄金期」とも言われる時代です。ベストセラーが次々と生まれます。
しかし、昭和末期となる昭和60年代(1985年)から読書率が低下していきます。
昭和末期から始まった読書の衰退


1985年〜1989年 映像メディアの普及
昭和60年代後半から平成にかけて、テレビのバラエティ番組やアニメがどんどん増えました。
特に、ファミリー向けの番組や深夜番組の増加で、多くの人が本を読むよりテレビを見る時間を優先するようになっていきます。
また、この頃はビデオデッキ(VHS)の普及が進み、好きな番組を録画して楽しむ文化も広がりました。
映画も気軽に見られるようになり、映像コンテンツが読書の時間を奪っていくことになりました。
1990年〜1999年 ゲームの普及
1990年代に入ると、スーパーファミコンやプレイステーションといった家庭用ゲーム機が大ヒットします。
ゲームはストーリー性のある作品も多く、本の代わりにゲームで物語を楽しむ人が増えいきました。
また、1996年には「ポケットモンスター」が登場し、ゲームボーイの人気も爆発。本を読む時間が、ゲームの時間にどんどん置き換えられていきました。
2000年〜2009年 インターネットの普及
2000年代に入ると、インターネットが一般家庭にも広まり始めます。
Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンが普及し、本を読まなくてもネットで簡単に情報を得られるようになりました。
また、携帯電話の普及により、移動中でもネットを楽しめるようになり、本を持ち歩く必要がなくなってしまいました。
2010年〜2019年 スマートフォンとSNSの台頭、電子書籍の普及と紙の本の減少
スマートフォンとSNS
2010年代に入ると、スマートフォンの普及で読書離れがさらに進みましま。
特に、X(旧:Twitter)やInstagram、LINEといったSNSが大人気になり、短い文章や画像・動画を見る時間が増えたことで、本をじっくり読む習慣が薄れていきました。
また、YouTubeなどの動画コンテンツも急成長し、動画を見て情報を得るのが当たり前になりました。
こうして「文字を読むより、映像を見て楽しむ」流れが定着していきます。
電子書籍の普及と紙の本
電子書籍は便利ですが、スマホやタブレットで他のこと(SNSやゲーム)ができるため「本を読むことに集中できない」という問題も出てきました。
また、紙の本を買う人が減ったことで、書店の減少も進み、ますます「本と出会う機会」が減っていきます。
歴史を振り返ってみてみると
こうして見ると、江戸・明治から始まる読書の普及率は1965年〜1985年までのピーク時まで伸び続けていき、読書以外の新しい娯楽・趣味が生まれていくことで減っていったようですね。
電車での読書も、この時代全体を通して行われてきていると調べていて記載がありましたが、新しい文化が生まれると衰退していく文化も生まれてしまうのは仕方ないとはいえ悲しいですね。
「読書の黄金期」を作った社会全体の動き


では最後に、昭和に迎えた「読書の黄金期」ですが、それまで読書比率が増えていった要因がどんなものなのか見ていきましょう。
① 文庫本・漫画の普及
昭和30年代以降、文庫本が安価で広まり、電車の中や通勤・通学中に読む文化が根付きました。 また、昭和40年代には『少年ジャンプ』『少年マガジン』などの漫画雑誌が大ヒットし、子どもたちも読書習慣を持つようになります。
② 教育の影響
戦後、日本の教育制度が整備され、義務教育の充実とともに国語の授業での読書推奨が進みました。
学校の図書館が整備されたり、読書感想文の宿題が定着したりしたことも影響しています。
③ 出版業界の成長
昭和時代は「出版文化の全盛期」とも言われるほど、本がたくさん売れた時代でした。
特に昭和40〜50年代には、小説だけでなくノンフィクションやビジネス書も大ヒットし、広い世代で読書習慣が根付いていきます。
④ 情報源としての役割
今のようにスマホやインターネットがない時代、本は貴重な情報源でした。特に新聞や雑誌を読むことが日常的であり、知識を得る手段として読書が重要視されていました。
まとめ


現代はスマホ1台でニュースを見ることやSNS、動画やゲームなど様々なことができるため、便利な世の中になりました。
しかし、『なぜ仕事をしていると読書ができないのか』(三宅香帆著/集英社新書)と現代の問題と読書を警鐘する作品も出版されており、まだまだ読書をする方は残っていると思います。
僕のように読書をし続ける人や、今後読書に興味を持ってくださる方が増えることを願い、今後も読書の記事を書いていきます。



次回は、読書を始める場合に、月にどれくらいお金があればいいのかご紹介していきたいと思います!
それでは最後までブログをお読みいただき、ありがとうございました。
また次回のブログでお会いしましょう。
参考URL