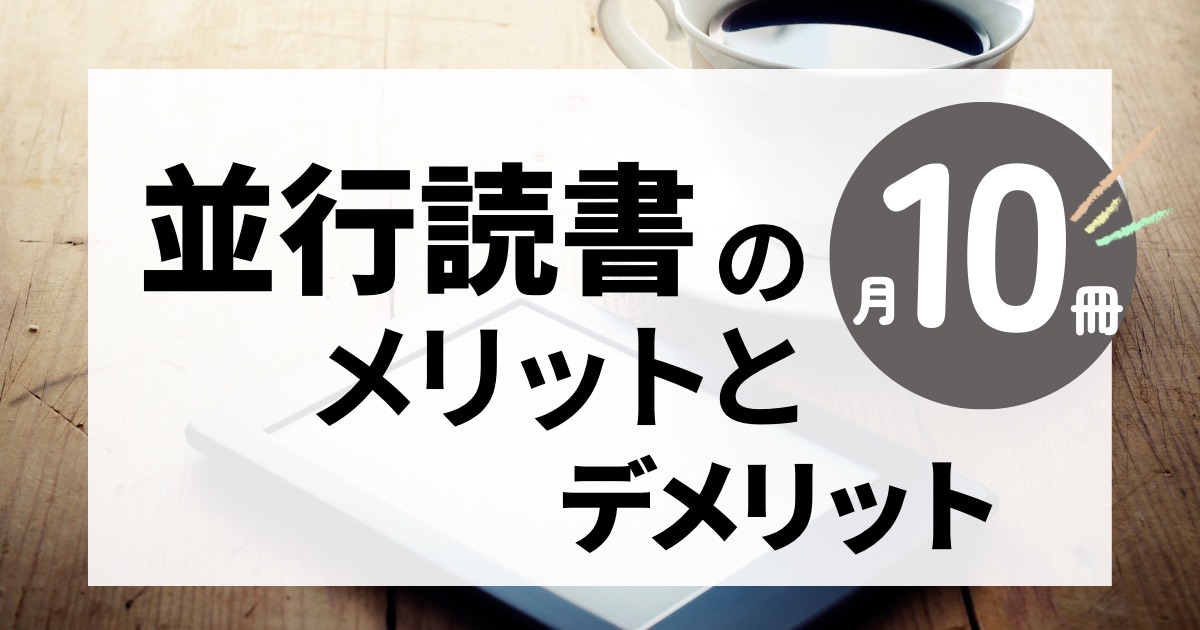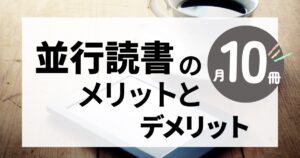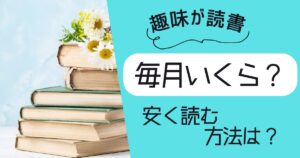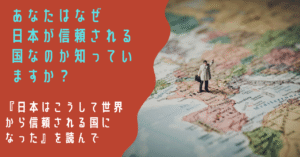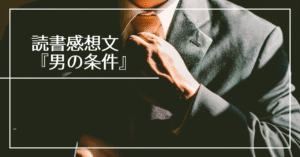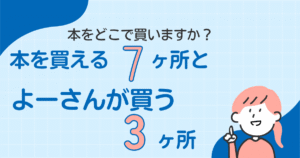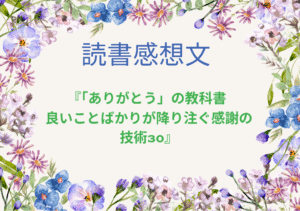Amazonのアソシエイトとして、よーさんは適格販売により収入を得ています。
 よーさん
よーさんこんにちは、よーさんです!
当ブログにお越し頂きありがとうございます。
今回は、僕が月に10冊読めた時の話をしたいと思います。
今回の記事を読むことで、以下のことがわかります
- 月に10冊以上の本を読む方法
- 同じ読書期間に複数冊本を読むメリットとデメリット
毎月これだけの数を読むのは難しいかもしれませんが、「多く読むにはこうすればいいのか」程度であくまでエンタメとして読んで頂けるとありがたいです。
そして、読書習慣の参考になる話となっておりますので、ぜひ最後までご覧頂けると嬉しいです!
10冊読むのに使用した月の読書時間


読書時間の多くは通勤乗車時の空き時間
これまでの記事でもお伝えしてきましたが、僕は通勤時間に往復4時間かけております。
家から駅、乗り換え、駅から職場までの移動時間もありますが、乗車時間は片道1時間10分です。往復だと2時間20分が仕事の日の何かできる時間です。
しかし、日記の記録や家族や職場への連絡もその時間に行っていることや、超満員のぎゅうぎゅう詰めでとても読めない状況もあるので、実際に読書しているのは往復約1時間です。
一般的には通勤時間が長くなるのは嫌がられますよね。
早く家に帰って少しでもゆっくりしたいですし。
でも僕は、この長い通勤時間が負担になっておりません。乗車時間中に本を読んだり、このようにブログを書いたり好きなことをできるので。
話は戻りますが、1か月基本22日勤務なので、合計22時間が僕の月の読書時間です。
1冊読むのに3時間で計算すると時間が足りない?それぞれの本の特徴
前回の記事でお話した、人が一冊本を読むのに3時間かかると書きましたが、この計算で考えると僕は読書時間に1時間の余りと7冊の読破をできていることになります。となると、残りの約3冊分、8時間足りないです。
しかし、10冊読めています。それはなぜなのか?
理由は3つあります。
22時間で10冊読破できた3つの理由


本のジャンルによって読み終わるペースに差がある
1つ目の理由が「本のジャンルによって読み終わるペースに差がある」 です。
その月に読んだ本のジャンルと冊数は以下の内容です。
- ラノベ 4冊
- お金 3冊
- ビジネス 1冊
- 生活 1冊
- 小説 1冊
ジャンルによって読むペースが変わる理由はさらに4つに分けられます。
文体や表現の違い
簡単な言葉で書かれたライトノベルやエッセイは、すらすら読めることが多いですが、専門書は難しい言葉が出てくるので、理解するのに時間がかかります。
読む目的の違い
娯楽として読む小説は速く読めますが、仕事のために読む本は、内容を理解して覚える必要があるので、どうしてもゆっくりになりますね。
ジャンルによる得意•不得意
興味のあるジャンルだと、集中して楽しく読めるから早く進めますが、苦手なジャンルだと読むのがしんどくなりペースが落ちてしまう場合があります。例えば、ファンタジーが好きな人は小説をどんどん読めますが、経済学の本には苦戦しますね。
既に知っている内容の部分は読み飛ばす
2つ目の理由が「既に知っている内容の部分は読み飛ばす」です。
これは、2つの理由があります。
退屈になってしまう
すでに知っている内容をもう一度丁寧に読むと、「あー、これ前にも読んだな……」って飽きちゃうことがあります。そうなると、読むのが面倒に感じてしまうので、飛ばしております。
時間の節約
本を読む目的は、新しい知識を得たり、物語を楽しんだりすることです。なので、もう知ってる部分は飛ばして、知らない情報や大事なところを優先的に読むことで、効率よく内容を吸収しています。
1冊の本を読んでいる期間に重ねてもう1冊読んでいた(平行読書)
3つ目の理由が「1冊の本を読んでいる期間に重ねてもう1冊読んでいた」です。
僕は、本を1冊の本を読んでて、飽きてきたり気持ちを切り替える時に別の本に替えて読んでいました。
これは2つの理由があります。
気分転換
同じ本を読み続けると、内容に飽きたり、疲れたりすることがあります。そんなときに別の本を読むと、気分を変えてリフレッシュできます。特に、難しい本を読んでいる途中でライトな小説を読むと、いい息抜きになります。
色々な知識を同時に吸収したい
ビジネス書で仕事に関する知識を得つつ、小説で物語を知る。様々な知識を本で得られるからこそ、たくさんの本を読みたくなります。
理由を挙げてから、思うこと
月に22時間本が読めるという、時間の多さもたくさん本を読める理由になりますが、やはり一番効果があったと思うことは「並行読書」をしたことだと思います。
同じ期間に読書をしてて、飽きてきたら本をしまって終わりですが、別の本を読んでいたら気分転換と一緒に新しい知識を得られて楽しいので続けて読むことができました。
苦手なことだとすぐに飽きやすい僕がこうして切り替えつつも続けて本が読めてるのは、「本のことが好き」なのが大きいのかもしれないですね。
では次に、一番効果があったと思った「並行読書」について話していこうと思います。
同じ期間に2冊読む「並行読書」のメリット3つとデメリット4つ
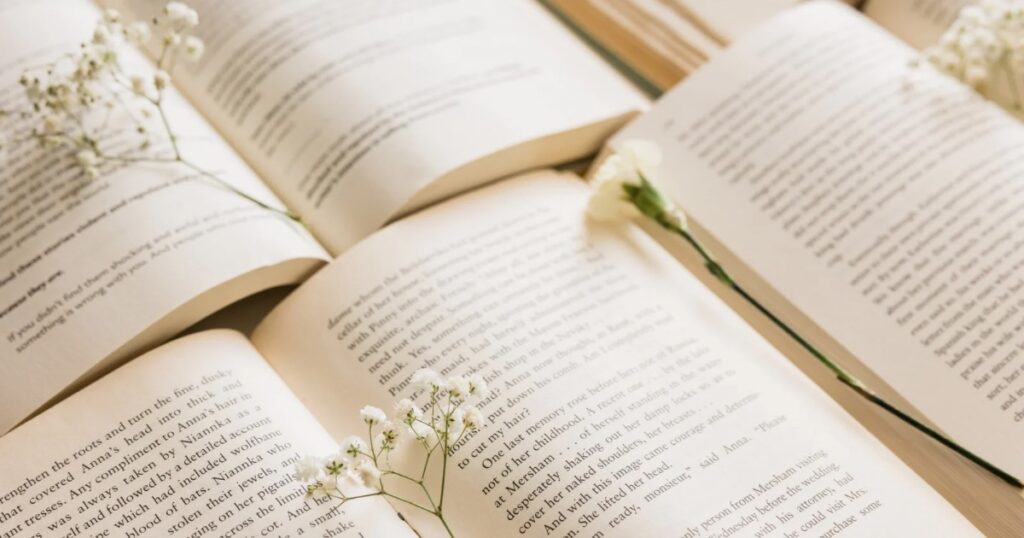
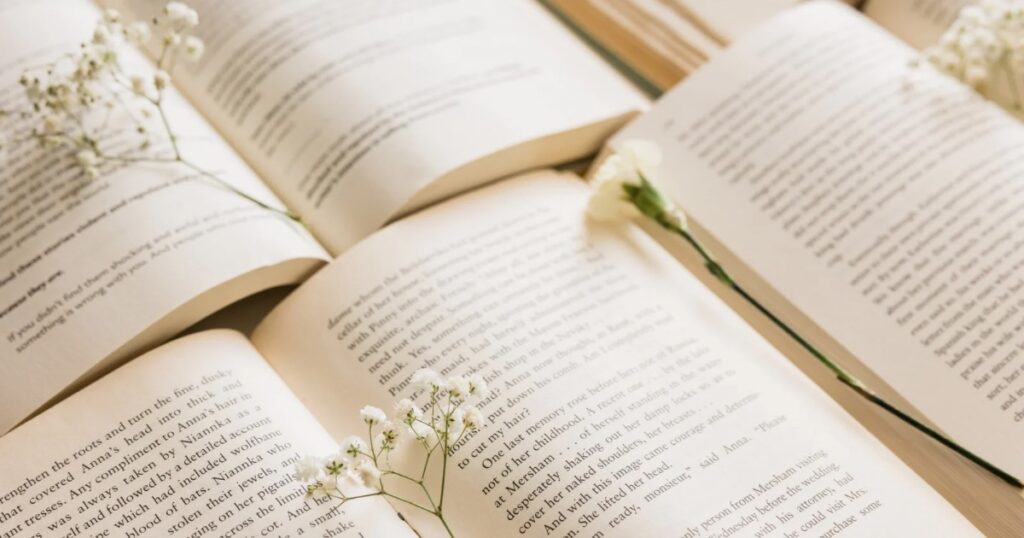
ここからは、本を切り替えてすぐもう一つの本を読む読書方法について深く掘り下げていきます。
「試してみようかな」と思ってもらった方のためにメリットとデメリットを書いていきます。
「平行読書」のメリット
読書が苦痛にならない
1冊に飽きたら無理に続けず、別の本を読むことで「読書=楽しい」という気持ちをキープできます。
新しい刺激を受けられる
違うジャンルの本に切り替えることで、気分転換になり、リフレッシュできます。
読書量が増える
いろんな本を並行することで、「この本をちょっとずつ、あの本も少し」という形で結果的にたくさんの本を読めることになります。
「平行読書」のデメリット
どの本もなかなか読み終わらない
1冊を途中でやめて別の本に移ると、結局どれも最後まで読まないままになる危険があります。大切なのは本を切り替えても、またその本に戻ってきて最後まで読み切ることです。
内容を忘れやすい
長く放置すると、「この本、どこまで読んだっけ?」となって、前の話を思い出すのが大変になります。
ストーリーの没入感が薄れる
小説などの物語は、一気に読むほうが世界観に入り込めますが、何度も切り替えると感情移入しにくくなります。
集中力が分散する
難しい本の場合、理解が中途半端になってしまい、ちゃんと身につかないこともあります。
結論
「飽きたらすぐに切り替える」のは、楽しく読書を続けるにはいい方法ですが、読み終わらない本が増えたり、内容が頭に入りにくくなるリスクもあります。
気分転換のために別の本を挟みつつ、メインの本もちゃんと進めるバランスが大事です。
まとめ


今回は、僕が最多読書できた月の話をしましたが、普段は僕もペースはこの月より遅いです。
しつこくなってしまいますが、せっかく読んでも身につかなければ、本を読んだ時間がもったいなくなってしまいます。
「こんな読み方もあるんだ」と知ってもらって、自分のペースを大切にして読んでいきましょう!
それでは、最後までお読み頂き、ありがとうございました!
また次回のブログでお会いしましょう!!