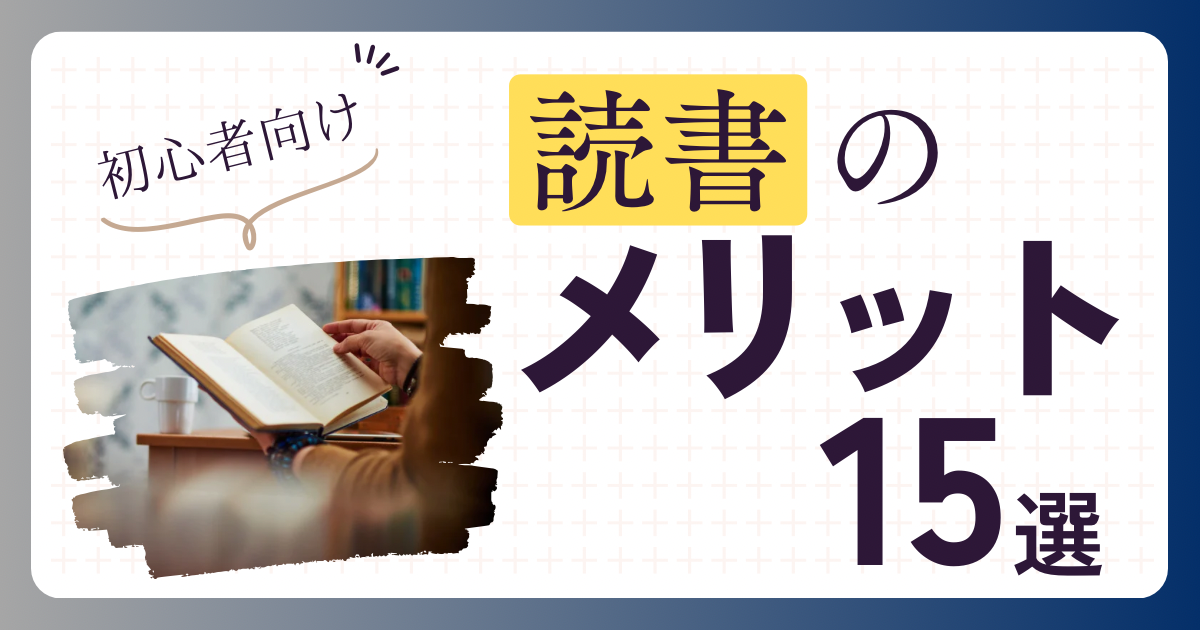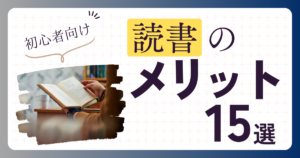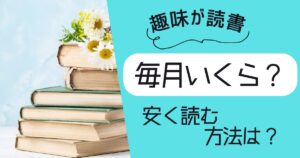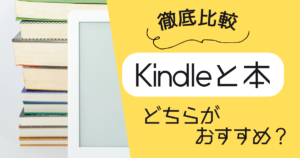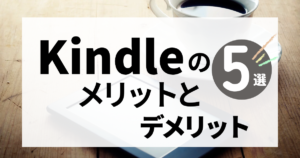今はSNSやyoutube、TVなど様々なメディアから情報を得ることができますね。
若い世代の方はSNSやyoutubeの動画から情報を得る人が多いと聞きます。
 よーさん
よーさんしかし、今でもどの情報を発信する媒体では、いずれも本や論文、機関からの発表内容が根拠として引用・紹介されることが多いです。
それは何故かというと、根拠として使用する情報は「信頼性の高さ」がとても大切になるからです。
「人が毎日歩く距離は2kmです」と話をした時、その話が事実であると証明するためには根拠になる引用情報が必要になりますね。
しかし、もしその引用情報が「実はウソでした」となったら、自分が持ち出した「人が毎日歩く距離は2kmです」という話の意味が無くなってしまいます。



そのため、根拠として引用する情報には、その情報を発信する事に
「責任」を持っている所からの引用が大切になります。
先ほど、根拠として引用されていると話した情報達には「誰が発信している情報」か分かるように、個人や組織の「作者の名前」が情報と一緒に記載がされています。
もし発表した情報が間違っていたら、『〇〇(名前)が出す情報はウソだよ』と広まってしまい、誰からも情報を見てもらえなくなってしまいます。
そのため、「作者」は「情報の価値」を守るためにも「正確な情報を伝える責任」が伴い、見に来てくださる方に信頼・信用してもらうためにも「質の良い」情報を伝えられるように努力されております。



さらに本は、「読めば作者と対話ができる」と言われるほど、本の作者は1冊の本を出すためにこれまで得た知識・経験をもとに、長い時間をかけて作られています。
いわば本は作者の「魂」です。本は作者がこれまで得た知識をぎゅっと形にしたものであり、私たちはその本を読むことで教えて頂くことができる、ありがたい事なんですね。
それでは今回は、本の大切さを知って頂けるために、これまでの僕の経験を踏まえ、読書によってどんな効果があるのかをお話していきます。
この記事でわかること
- 読書にはどんな効果(メリット)があるのか
- 読書による効果と、「日常生活」に「本の効果」を活用する例
「すでに読書をしている方」「普段はしていないが読書に興味がある方」等々、読書に触れる・触れたい人ににお読み頂くことで、「読書」のすばらしさを知って頂けたらいいなと思います。
読書の効果〜15個の読書のメリット一覧〜
それでは、さっそく本の効果のお話です。
項目に分けてみましたが、なんと15個の効果が得られます。
- 知識や教養を得られる
- 語彙力アップ
- コミュニケーション力アップ
- 文章力アップ
- 想像力アップ
- ストレス発散
- 悩みや課題の解決するヒントが得られる
- 会話のきっかけやネタになる
- 効率的に情報収集できる
- 色々な価値観を知れて視野が広がる
- 失敗を学び自分の成功に繋がる
- アイデアが得られる
- 論理的思考が身につく
- 集中力鍛えられる
- 脳が活性化する



それでは、次にそれぞれの項目についての話と、僕の経験も交えて解説していきます!
読書で物知り博士に〜(1)知識や教養を得られる~
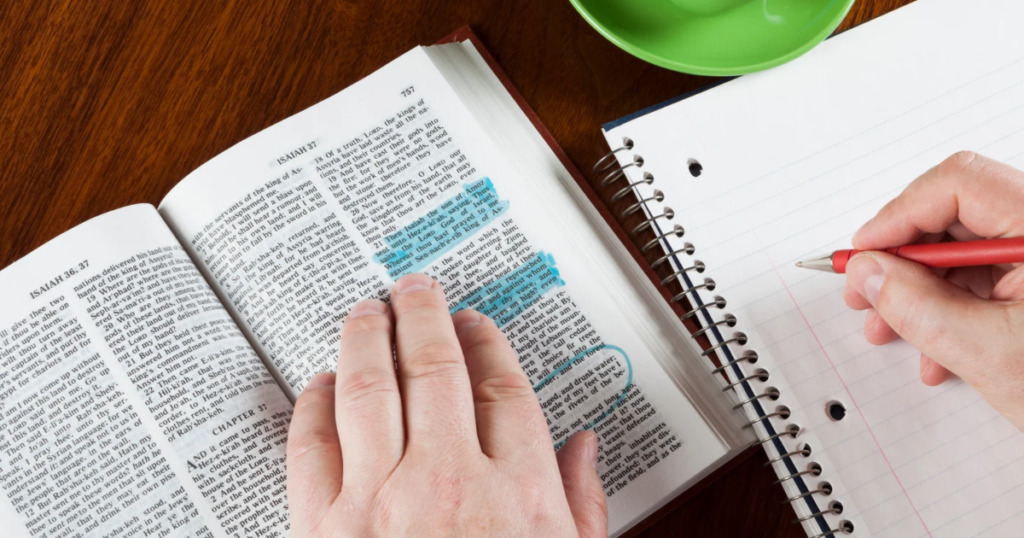
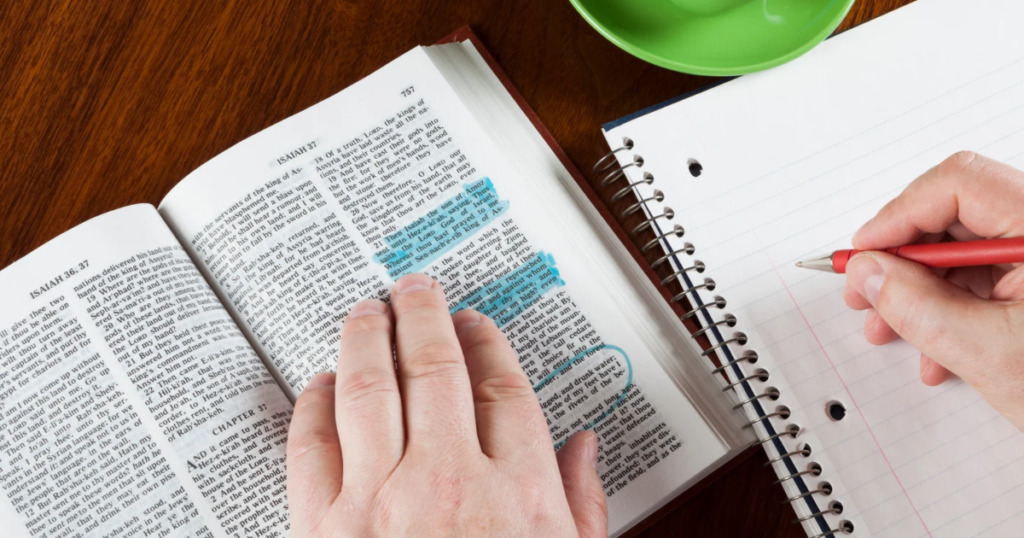



読書をしていると本の内容で自分の知らなかった事が書かれていて、「新しい知識を知ることができた」と経験したことがある方が多くいらっしゃるんじゃないでしょうか?
経済、歴史、文学、哲学、地政学などなどさまざまな分野に本がありますが、本には「知識・教養」が凝縮されています。本を読むことで、自分が知らなかった「知識・教養」に触れる機会が増えるため、知識が大きく増えやすくなります。



僕は誰かに話をすることが苦手なので、うまく話す方法がないかと「話し方」を学ぶ本を探した時があります。
その際に『人は話し方が9割』を見つけ、「話は相手7割、自分3割で話すのが良い」と知り、話すより聞くことが大切と知り、あれから緊張せずに話せるようになりました。
また、知識をつけたい分野の本を集中的に読み1つの分野の知識を深める、幅広い分野の本を読んで広く知識を得るのもいいですね。
・一つの分野の知識を深める:江戸時代の歴史を知るために「当時どのような統治をしていたか幕府の役人視点からの本」「幕府の統治を受ける農民や町民の視点からの本」等の様々な視点からの本を読むことで、時代の全体を知ることができますね。
・幅広い分野の知識を得る:自分の興味のある「自己啓発」の分野だけでなく、将来の自分の生活が安泰になるために「お金・投資」の分野をの本を読む、最近体調を崩しやすいから「健康」の分野の本を読む等、様々な分野の知識を知り、いろんな分野でも知識が役立つようにするのも良いですね。



僕も最初は「お金について知りたい!」と思い、「お金・投資」の知識を深めるためにこの分野の本を片っ端から読んでいました。
しかし、次第に新鮮な知識を得られにくく新しい知識を得たいと思うようになり、今は「渋沢栄一」や、「食生活」といった様々な分野を知りたくなり、広い分野の本を読んでいます。
一つの分野を深める際は、様々な視点・著者の考えを知るために5冊以上読むことが推奨されていますね。
なぜかというと、分野の知識を深めるために本を一冊だけ読むと、読んだ著者の知識だけを知ることになり、知識に偏りができてしまうからですね。
小説やエッセイ、詩集、歌集などを読むのもいいですね。
場面を表現する文を読んでイメージしながら読めば「表現力」が向上するといった効果が期待できます。



読書に慣れていったら、応用として本の内容を理解する時間をとることは重要であり、いいことですね。
改めて時間をとることで、読んでいた時に「そうなのかな?」「自分ならこう考えるな」と感じた部分について自分なりに考えを深めることができます。加えて、自分の中で使っていくことで教養として身につけることができます。
読書をすることで、知らなかった知識や教養を「あ、この内容、この前読んだ本の知識を生かせるな」と内容が結ばれていき、一冊の本でも多方面の知識から考え、身につけることができますね。



僕は、「お金・投資」の本を読む中で最初の本で「固定費を抑えると節約に繋がる」と知り、次に読んだ本に「貯金には節約が大切」と知ったことで「固定費削減は貯金に大切」とそのまま知識を活かせました。
また、「他にも節約の方法はあるのかな」と興味が広がる可能性もあり、次々と取り入れることで生き方や考えが変わるきっかけにもなるかもしれません。
わかりやすい説明で頭が良さそうに見られる〜(2)語彙力•(3)コミュニケーション力•(4)文章力の向上





ここでは最初の15項目で挙げた
2.語彙力が豊かになる
3.コミュニケーション力アップ
4.文章力アップ
が共通する内容となりますので、3つをまとめてご紹介していきますね
語彙力
本は読者に内容が伝わりやすくするために様々な言葉を使っていて、本を読んでいるとそれらの言葉に触れることができます。そのため、言葉に触れることで多くの言葉を知ることができ、生活の中で言葉を使い分けることで、相手にわかりやすく伝える能力が身に着きます。



説明をする際、相手がどれくらいのことを理解・知っているかで、相手に合わせた説明が必要になりますよね。
僕は仕事でパソコンの説明をする際、パソコンに詳しくない方には専門用語を別の言葉に置き換えて説明します。
置き換える際、相手にしっくりくる言葉を選ぶために様々な言葉を知っている必要があり、「言葉を使い分ける力=語彙力」になります。
コミュニケーション力
語彙力が上がれば、相手に合わせた言葉で話ができるようになります。相手も自分に合った言葉なので内容が頭に入りやすくなり理解も深まります。
相手がわかりやすい話をすることで「あ、この人は話が上手だな」と思ってもらえることができ、「コミュニケーション力が高い」と思ってもらえるようになります。



僕も以前は、自分が知っている少ない言葉でむりやり話をしていたので理解しづらく「うーん」と首を傾げられてしまうことがありました。
しかし、本を多く読み言葉を知り、相手に合わせた言葉で話ができるようになってから「なるほど」と言ってもらえることが多くなりました。
文章能力
もうくどくなってしまいますね(汗)。
「コミュニケーション力」と同じく、読みやすいように「読書で得た言い回しや表現の仕方」「言葉の使い分け」等を活用して文章を作ると、言葉の表現が豊かになり、わかりやすい文章を作りやすくなり、文章能力が上がるのです。



読み手の方にせっかく読んで頂いているのに「この人は何が言いたいんだ?」となってしまったら頑張って作った文章もさみしいですよね。
「会話」なら言葉だけでなく「声のトーン」や「表情」「ジェスチャー」などの情報を加えることでより伝わりやすくなりますね。
しかし、「文章」は伝えたいことを「文字」で伝える必要があり、かつ想像を読み手に委ねる必要があるので表現が難しくなります。
場面や状態を頭の中ですぐに「パッと」イメージできる〜(5)想像力アップ〜


「想像する」という言葉を聞いた時、一番何が想像しやすいですか?多くの人は、小説に出てくる場面を、どんな感じなのか想像するのがしやすいのかなて思いますが。
小説なら、登場人物がどんな状況で、どのように話が進んでいくのか文字で細かく描かれているので想像しやすいですよね
皆さんもイメージがしやすかったように、結論から言うと1番想像力アップにつながりやすいのは、小説です。
なぜかと言うと、
- 言葉や情景を思い描く
- 登場人物の気持ちを想像する
- 物語の続きを考える
といった様々な想像をしながら読むので、想像する回数が多く想像力が鍛えられるからです。



読書はただの情報収集じゃなくて、頭の中で「映像を作る」「気持ちを考える」「ストーリーを想像する」というトレーニングをしています。 本を読むほど、想像力はどんどんパワーアップしていきます。
その経験が、日常でも相手のことを考えて寄り添い、共感し言葉を伝えられることにつながります。



ちょっと照れくさい話ですが。
僕はラブコメ要素のあるライトノベルを読むのですが、その中で「男性と女性で手をつなぐ」シーンがあり、自分と妻とでその場面を重ねて想像したことがあります。
さらには、最近手を繋いでいないなと思い、二人で出かけた際に手を繋ぎにいったことがあります。
読書して気持ちもスッキリする〜(6)ストレス発散〜
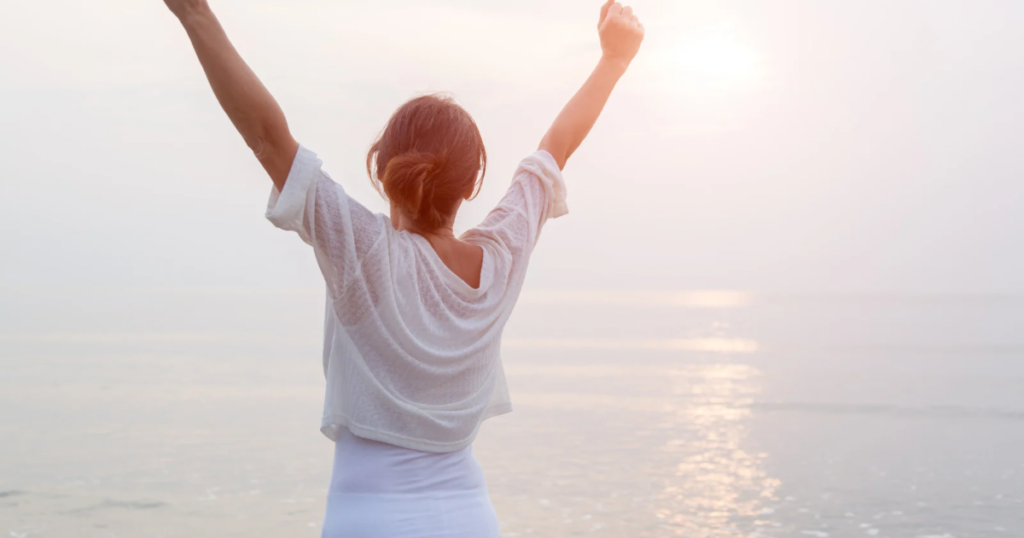
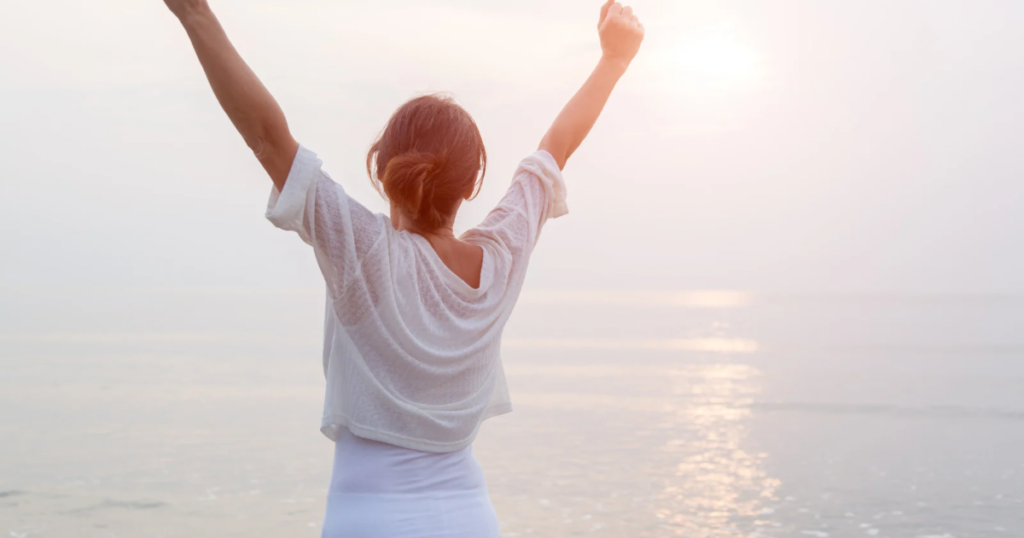
本を読んで、「あー、すっきりした」てなったことはありますか?
自己啓発本やレシピ本といった実用書を読んで悩みが解決した時、小説で主人公がケンカしたけど仲直りしてハッピーエンドになった時など、「すっきりした」って思いやすいんじゃないかなって思います。



後は、スポーツマンガを読んでいて、主人公チームがピンチの時に試合時間残り数秒で逆転したシーンを見たとき「すっきり」しますよね
本を読むことで「すっきり」できる4つの理由
- 現実を忘れて物語の世界に没頭できる
- リラックス効果がある
- 感情を発散できる
- 悩み・課題のヒントを見つけることができる(次の章でお話しますね)
といった事ができるからですね。
こうして理由を見てみると、「あ、経験あるかも」となった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
リラックス効果
いくつか理由があり
①集中力の切り替え:本を読むと、普段の悩みやストレスから意識が離れて、物語や知識の世界に没頭すると思います。これが「気分転換」になり、頭の中のごちゃごちゃが整理されやすくなります。
② ゆったりしたリズム:読書は基本的に静かで、自分のペースで進められますよね。 ページをめくる音や、活字を追うテンポが自然とゆっくりしていているので、心拍数や呼吸もそれに合わせて落ち着いていきます。
③ 想像力の働き:文字を読むと、頭の中で場面や登場人物を思い描きますよね。その「想像の世界に入る」ことが、まるで別の世界に来たような気分になり、現実を切り離して気分転換になり、リラックスに繋がります。
④科学的な裏付け:研究でも「6分間の読書でストレスが約6割減る」というデータがあるほど、心を落ち着ける効果が確かめられています。
特に、好きな小説や心温まる物語を読むと、気持ちが穏やかになってリラックスしやすいですね。



僕は、本を読むことがそもそも好きなので、どんな本でも読むだけでリラックス効果が得られます。
感情を発散
「カタルシス効果」とも言われ、怒り•悩み•不安といった心のネガティブな感情を吐き出すことで、気持ちの安定を取り戻すことです。



本の中で登場人物が泣いたり笑ったりすると、自分も一緒に感情が動かされるって経験ありませんか?登場人物と一緒にネガティブな感情を吐き出すことですっきりした気持ちになります
「このキャラの気持ち、わかる……!」って共感すると、自分も同じなんだと思えて自分のモヤモヤした気持ちもスッキリすることがあります。



ラブコメで、付き合いたての主人公カップルがなかなか手をつなげいシーンがあると、「ああ、わかる!不安で緊張するよね!」て読みながらドキドキした時あります
また、感動する作品を読んで、涙を流すのも、いいストレス発散になりますね。
涙を流すと、リラックスするスイッチ(副交感神経)が働いて心が落ち着き、ストレスも一緒に体の外へ排出されるから、スッキリしてストレス発散になります



涙を流す前はあれだけ心が乱れてたのに、涙を流したらなぜかスッキリしてるって経験、皆さんもありますか?
「考え」「知恵」で吹きとばせ!〜(7)悩み•課題の解決のヒントが得られる〜


悩みや課題があった時、本を開いて解決できたって人は多くいらっしゃるんじゃないでしょうか?
例えば、学校や職場で「~をやってきなさい」「~を作ってきなさい」と言われ、「えー!!突然できないよ!!」てなったことはあつかなって思います。今ある知識や経験で解決できそうな事なら悩むことは無いですが、それだけでは解決できないことも突然出てくることもありますよね。
誰かに相談してアイデアを頂くのも一つですが、まわりに相談することがができない場合は自分で解決しないといけません。そんな時に、悩みや課題を解決する答えのヒントを探しに本を利用するのが、とてもおすすめなんです!



僕は、小学生の夏休みで「自由研究」があり、いきなり研究をやれと宿題をだされてもすぐに「何をやろうか」アイデアは出てきません。そんな時に、研究のお題にいい「考え」「アイデア」を探すために本をよく利用していました。
なんでおすすめなのか、理由は大きく3つあります。
- 「新しい知識や視点を得られる」ので、自分が思いつかなかったアイデアを得られやすい
- 読書に集中することで、現状から気持ちが切り離されるため「客観的になれる」
- 新しい知識をもとに、『この方法ならこんな結果になりそう』、『私ならこうするな』と、応用的な事を考えられるようになり、「思考力が鍛えられる」
新しい知識や視点を得られる
この記事の最初にも書いた、本は作者がこれまで得てきた知識を集めたものであり、その中には自分が知らなかった考え方や経験がたくさん詰まっていますね。自分が知らなかった内容に触れれば、それは「新しい知識や視点」として自分の中に取り入れていくことができます。
例えば、本の中で紹介されている偉人の成功談や失敗談、作者自身がこれまで行ってきたことなど読めば、どんなことをすれば成功・失敗しやすいのか知ることができ、「今後は成功のためにこれをやろう!」とか「失敗を避けるためにこれはやめよう」と気づくことができます。



悩みや課題の解決も本を開く一つの理由ですが、自分の興味がある分野の本を読むのも立派な理由ですよね。
興味を持っている内奥は知識を覚えておきやすいし、近いタイミング活用できるチャンスが来ることもありますね



例えば、近年では「お金・投資」に関する本で「投資で良い銘柄は~」や「節約のために~は避けるべき」など具体的にどんなことをするのが良いか書いてあります。
自分がまだ行っていない事があれば、それを取り入れることで自分を変えていけるし、本を活用できますね。
また、自分の中で知識が増えると、普段見えている世界も見方が変わっていきますね。自分の視野が広がって、今まで思いつかなかった解決策が見つかることもあります。
客観的になれる



悩んでいるときって、つい感情的になったり、同じ考えにとらわれたりしまいがちです。
でも、本を読むと、一度その悩みから距離を置いて冷静に考えられるようになれるんです。
結論を言うと、「心が別の世界に行けるから」になります。
本を読むと
① 文字から頭で映像•音•匂いのイメージを作る
↓
② 現実よりも物語に集中するために、本を読むことに集中する。それにより現実から離れる
↓
③「①②」により 、実際に体験した時に働く頭の部位と同じ部位が働き、イメージが実際に体験してるように感じる(≒仮想体験)



悩みのことばかり考えていると、その事に頭が一杯になり、冷静さを失いやすいです。
さらにぐるぐる同じことを考えて、余計に不安になったりもしますよね。
しかし、本を読めば、物語や知識の世界に意識が向き、悩みから少し頭を切り離せます。
特に小説を読むと登場人物の考え方や行動を客観的に見ることができますね。
さらに、「もし自分がこの立場ならどうする?」って考えることで「別の見方」が得られます。



小説を読んで、主人公と同じ気持ち•立場になったと思って読むとより臨場感が生まれて良いですよね。
朝井リョウさんの「生殖記」を読んだ際は、同性愛の気持ちに触れて、なんだかドキドキした気持ちになりました。
思考力が鍛えられる
これは、本を読んだ多くの方が経験したことあると思います。
本を読むことで、論理的に考える力や問題を整理する力がつきます。
それには3つの理由があります。
1. 善悪や価値観にふれるー例えば小説を読むと、物語の中に正義や悪、友情や裏切りなど、多くの人間の価値観が出てきますね。読むことで「これは正しい?間違ってる?」と自分なりに判断する機会が増え、考え方が深まります。
2. 自分の世界を広げてくれるー読書は、自分が普段関わらない社会や文化の考え方を知るチャンスになります。違う考え方にふれると「自分の正しさだけが絶対じゃない」と気づくことができるので、より柔軟で倫理的な視点を持てるようになります。
3. 振り返りを促すー本を読むと、ストーリーや情報を通じて「自分だったらどうするか」と振り返る機会になります。それが「善く生きるってなんだろう?」という倫理的な問いにつながります。つまり、読書は「他人の人生を借りながら、自分の心の中でシミュレーションする体験」だからこそ、倫理的な考え方が鍛えられます。



ただ本の文章を読むだけでなく、「自分だったらどうするか」や「これは正しい事なのだろうか?」と考えながら読むことで倫理的思考を身につけていくことに繋がっていきますね。
また、特に自己啓発書や哲学書、心理学書といった分野では、「物事をどう捉えるか」が大事になりますので、「捉え方」を考えながら読んでいくうちに自分の考え方をアップデートできます。



人との関わり方で悩んでいた際に、「アドラー心理学」についての本を読み「『変われない』のではない。『変わらない』という選択を自分でしているだけ」という言葉を知りました。
「『現状』を変えられないと自分で思っていただけで、自分が変わろうと思えば変えていけるのでは?」とヒントを得られたことで考えられるようになり、そこから考え方の幅を広げられました。
もう話のネタ切れはさせない?!〜(8)会話のきっかけやネタになる〜


本を読んで、読んだ後に「あぁ、本の事を誰かに話したい!」てなった経験、本を読まれた方は多くの方が経験あるのかなって思います。
特に、実用書で知ったこと、雑学といった自分が知らなかったことを知れたら「誰かに話したいな」っててなりやすいですよね!



僕と妻2人とも健康を大切にしてて、本の中で「糖質は抑えると疲れの軽減に繋がる」と知ったとき、すぐに教えて共有したいなって、会話のきっかけになりましたね。
また、話す際もただ本で得た知識をそのまま相手に伝えるのではなく、相手が一番わかりやすい言葉に直して話すと「(3)コミュニケーション力アップ」にもつながっていきますね!
会話のきっかけ、ネタになる理由3つ
- 本を読んで知らなかった知識を知ることで、「知識が増えて話題が広がる」
- 知った知識の中で聞き手に興味を持ってもらえる内容、知っている知識+αになる内容があれば「共通の話題ができる」
- 「『知的な人』という印象を持ってもらえる」事で、話しかけてもらいやすくなる
知識が増えて話題が広がる
ここの項目「7」の最初にも書いた、本の話をするきっかけに一番なりやすい内容ですね。
本を読む事で、新しい情報や考え方を知ることができるので、その内容を誰かに話すために会話のきっかけになります。
特に、自分の「推し」があれば、「推し」は自分がもともと好きな内容なのでどんどん本の内容も入っていきますし、得た内容を話したくなってさらに会話が弾みやすくなりますね。



僕は、USJを盛り上げ直した森岡毅さんが好きで、森岡さんが手がけた「ジャングリア沖縄」誕生に関する「心に折れない刀を持て」を読んだ時は、森岡さんの熱意を誰かに話したいって興奮しました
また、得た知識が話す相手に興味を持ってもらえそうな話だったら、それを話せば自然と話に興味を持ってもらえることができるし盛り上がりやすくなりますね。
共通の話題ができる
読んだ本が友人や家族といった人から紹介してもらった本だったら、読んだ本の話を紹介してもらった人と話せばお互いが知っている話題になり、話が弾むようになりますよね。



よーさんから「これいいよ!」と度々話が出ていた「三国志」を私も興味を持ち、読んでみたらハマってしまい、「三国志」の話でお互いに盛り上がるようになりました



一緒に感想を言い合ったり、おすすめの本を教え合ったりするのも楽しいですよね。
特に、「ハリーポッター」といった人気の小説や、「頭のいいひとが話す前に考えていること」といったビジネス書は読んでいる人が多いので、多くの人の共通の話題として盛り上がりやすくなりますね。
『知的な人』という印象を持ってもらえる
今度は逆に、共通の話題としてではなく、相手が知らない知識を相手に伝えると「この人、いろんなこと知ってて面白いな」と思ってもらいやすくなります。
ただし、相手がどんな話に興味があるか、本の話をする前に会話の中で相手のことを知ることはとても大切ですね。興味があるのかもわからないのに、いきなり話を始めると「この人、話が長いな」等と悪い印象に繋がってしまいますので注意しましょう
相手が知らないけど興味がある話なら、自然と「もっと聞きたい!」って思ってもらえることもあり得ますね。
また、日常的な会話の中でも、いろいろな知識があれば話題にも困らないし、話の中から話を広げてさらに会話を楽しむといったことも可能になりますね。
本で時間を効率化させて時短ができる!〜(9)効率的に情報収集できる〜


これまでの話でも書いてきましたが、本はたくさんの知識・情報が載っているため、効率的に情報収集ができます。では、なんでなのかというと、大きく理由は5つあります。
本で効率的に情報収集ができる5つの理由
- 情報が整理されている
- 信頼性が高い
- 必要な情報を取捨選択しやすい
- 集中して学べる
- 記憶に残りやすい
情報が整理されている
本は、著者が長い時間をかけて「著者がこれまで得た情報をまとめ、本に入りきる量にしつつ論理的に整理」をした内容になっています。そのため、一冊の本を読むだけでも相当な量の情報を得ることができます。
また、今はネット記事やSNSといったデジタルメディアからも膨大な情報を得られますね。しかし、それらから正確な情報を得ようとした場合は注意が必要です。なぜなら、得られる情報は嘘が混ざっていることもあり、全てをそのまま信じるには注意が必要です。
信頼性が高い
本として出版される情報は、本を書いている著者だけでなく、編集者や専門家といった様々な方のチェックが入り、1冊の本が作られていきます。
そのため、念入りに内容を確認してから本が出版されるので、間違った情報が広まりやすいネットよりも、信頼性の高い知識を得やすいです。



この記事でも最初にお伝えした、「エビデンス(根拠)」として使われるのも、こういった理由があるからですね
必要な情報を取捨選択しやすい
本は、自分の読みたい所にいっきにページを飛ばして、自分の読みたいところだけ選んで読むというのがしやすいですよね。
自分が興味ない所を飛ばすことで時短にもなり、タイパも良くなります。
また、多くの本には「目次」や「索引」があり、自分が知りたい部分だけを効率よく探せます。



本の読み方を紹介する本で、速読では情報の入力が速すぎて頭に入りにくく、「目次」から自分が読みたい部分だけを普段の読書の速さで集注して読むのが良いとありました。
デジタルメディアなら知りたい情報をすぐに見つけやすくて便利ですが、膨大な情報の中から本当に正しく•必要な情報を選ぶのは意外と大変ですよね。
集中して学べる
本なら、文字を通して本の世界に入っていき、「疑似体験」できるほど内容に集注することができます。
デジタルメディアであるSNSや動画は次々と新しい情報が流れてくるため、一つのことをじっくり学ぶのが難しいです。



僕も、YouTube動画を見て情報を集める時があります。
動画だけを集中して見ていたら情報を得やすいですが、何かをしながら見てることが多く、そうすると集中力が減って覚えていられる量も減ってしまいます。
しかし、本なら読むペースを自分でコントロールできるし、興味のある読みたい部分を選べばさらに集中して知識を深めることができます。
記憶に残りやすい
本を読んでいるときに、「この内容はこういうことか」と言った考えることで脳がその情報を整理しながら理解しようとします。
また、内容を考えるために内容を脳に記憶、記憶した後に内容の整理として内容の記憶が使用されます。内容を「覚える」・「保持する」・「取り出す」という記憶に必要なプロセスが自然と組まれており、記憶に残りやすくなっています。



「覚える」・「保持する」・「取り出す」を専門的にいうと「記銘・保持・想起」といいます。
読みながら考える他に、人に話すことでも記憶に残りやすくなりますね。話すことにより、自分の声を自分の耳が聞いて、改めて内容が脳に入っていくので再度「覚える」機会ができます。
さらに、線を引いたりメモを取ったりすると、さらに記憶に残りやすくなりますね。メモや線を引くことで大切な部分が目に入りやすくなりますし、「ここは重要な部分」と認識しやすくなります。
また、本なら見つけた情報は信頼性が高いのでそのまま活用することができるし、索引で知りたい事項
や語句がわかっていればダイレクトに知れるのもいい所ですよね。
見る世界を広げよう!~(10)価値観を知れて視野が広がる~


例えば、京都にある清水寺を見たとき、あなたはどんな感想を持ちますか?「奇麗だな」「舞台から下が高いな」など思うかもしれませんね。しかし、本で様々な知識があると「舞台から京都タワーが見ることができる」「造られた奈良時代の背景から見える清水寺」といった、同じものを見ていても様々な視点から見ることができます。
では、なぜ本を読むと色々な価値観を知れて視野が広がるのか、理由は3つあります。
- 自分とは違う様々な人の立場や考えに触れられる
- 著者の視点を通して世界を見ることができる
- 自分の考えを見つめ直すきっかけになる
自分とは違う様々な人の立場や考えに触れられる
本に描かれている、自分とはまったく違う性格の人や、別の国・時代・環境で生きている人の気持ちや考え方を「体験するように知る」ことができる、という事ですね。



地政学から見たら、日本は海に面している「海洋国家」、大陸にあって陸続きの国家は「大陸国家」といいます。大陸国家は外国と隣同士なので外国に移動しやすいですが、反面周りの国からの影響も受けやすく、どんな立場、どんな考えといった、環境が違う世界を触れることができます。
あとは、僕はそうだったのですが、学生時代に恋人がいなかった方も中にはいるのかなと思います。学生時代の恋愛はどんなことができたのか恥ずかしながら想像がしにくいのですが、主人公が学生のラブコメのラノベを読むことで「学生時代に恋人がいたら、帰り道デートや文化祭を一緒に回る」といったことを知ることができたし、その時にどんなことを感じたか知ることができました。
まとめると
- 著者の表現やテーマを通して知る → 「著者の視点・考えを知る」→書き手の考えを理解する体験
- 登場人物を通して感じる → 「いろんな立場・考え方に触れる」→登場人物の心を感じる体験
著者の視点を通して世界を見ることができる
本には、作者の方が見た視点・世界での内容が書かれていますね。これまで私たちが見てきた視点・世界を作者の方が全て同じく見ていることは考えにくく、言うなれば自分とは違う時代、国、環境で生きる人の視点や世界、考え方や価値観をしることができます。



たとえば、日本で育った人が海外へ旅に行った方の本読めば、その方が外国へ訪れたときに感じた事や考え方、その国の文化について知ることができ、「こういう国もあるんだ!」「こういう考え方もあるんだ!」と気づくことができますね。
実際にその国に行かなくても、新しい価値観を知る手段になります。
また、実用書もこれに当てはまりますね。多くの本は、作者が「これまでにやってきた事」を元に書かれている本が多く、作者の経験が詰まっています。実用書を読むことで、作者がこれまで行ってきたことを疑似体験ができ、作者が得てきた情報を得ることができます。
また、作家や研究者は、それぞれ独自の視点や経験を持っています。
自分の考えを見つめ直すきっかけになる
本を読むことで、「自分はこう思っていたけど、もしかして違う見方もある?」と考えることが増えます。



「努力がすべてだ」と思っていた方なら、成功は環境や運も関係するという本を読めば、「努力だけじゃないんだ」と新しい考えを持つきっかけになりますね
生活していると、自分視点で物事を考えやすいですが、いろいろな人の価値観を知ることで「あ、この人は実はこう考えてるのかも」と1歩下がって現状を見るのに役立ちますね。
どんなことが成功方法なのか知ろう!〜(11)失敗を学び自分の成功に繋がる


ことわざにも「失敗は成功を教える」や、「転んでもただでは起きない」などあるように、失敗から生まれた話は世の中には数多くあります。



僕も、何も知らなかった学生時代は「世の中の成功者はみんな失敗しないからこそ、そこまで上り詰められたんだ」と思っていました。
しかし実際は逆で、成功者たちほど多くのことに挑戦をし続けてきたので、人よりも多くの失敗を経験していることが多いです。失敗を生かし、次に繋げてきたからこそ成功者たちは成功してきたのです!!
どんな方もこれまで小さなことから大きな失敗を含め、様々な失敗をしてきていると思います。ですが、失敗をしても挫けずに、次に生かすことで成功に繋がっていきます。
まとめると、本を読んでこれまでの失敗譚を知ることで「どんなことをすると失敗する」「これをすると成功しやすい」と、過去の知識や経験を学べることができます。
なぜ失敗を知ると成功に繋がるのか、具体的な理由は4つあります
- 失敗のパターンを知れる
- 成功した人の考え方や行動を学べる
- 問題解決のヒントを得られる
- 物事を客観的に考えられるようになる
失敗のパターンを知れる
歴史やビジネスの本には、成功した人だけでなく、大きな失敗をした人の話も載っていることがあります。本にはビジネス書であれば「人と話す時に会話のキャッチボールではなく一方的に話してしまう」や、歴史では「エジソンが発明の研究に没頭しすぎて妻の顔を忘れて大激怒させる」などあります。
その人たちが「なぜ失敗したのか」「どうすれば避けられたのか」を知ることで、自分が似た状況に立たされた時に同じミスをしないように気をつけることができます。



「投資をすると損をする」とよく聞きますが、ではなぜ損をするのか気になり、投資の本を読んでみたら「1種類の個別株を大量に買ったことで、値下がり時に大損した」や「常に株価チャートを見ないといけないから時間の損失が大きい」など、失敗の原因を知ることができました。
成功した人の考え方や行動を学べる
失敗とは逆に、成功した人がどうやって成功したのか書かれている本を読めば、その自分の行動に取り入れることで、成功の確率を上げられるようになりますね。
そのため、失敗例を知ってリスク回避を心がける事は大切ですが、成功の方法を知ることも大切ですね。



僕もセミFIREを目指してますが、すでにFIREをした人の本で、「コンビニは使わない」「電車は2駅先まで歩く」などすぐに自分が取り入れられることがあれば、取り入れることで自分も成功に近づきますね
本で紹介している著者が行っている事が、今の自分と環境•状況が近ければ、そのまま真似するということもできますね。
成功への1番の近道は成功者の真似をすることなので、どんどん成功の方法を知り、真似していくと自分の成功も近づきます。
問題解決のヒントや答えを得られる
問題•課題があって、答えや解決策が知りたいと思って本を開く経験がある方は多くいらっしゃるといと思います。
そうです!本には問題解決のヒントや答えが得やすいです。



たとえば、人間関係で悩んでいるなら心理学の本、勉強がうまくいかないなら効率的な学習法の本を読むと、今まで気づかなかった方法を知ることができますね。
本にはたくさんの情報がありますので、その中から自分の知りたい答えやヒントを見つけることができたら、課題•問題の解決につながりますね。
物事を客観的に考えられるようになる
客観的になるのは、この3つのことができるからなんです
① 自分とは違う考え方や立場を知れる
本の中には、いろんな人の意見・価値観・生き方が書かれていますね。それを読むことで、「あ、自分とはちがう見方もあるんだ」と気づけたり、「他の人ならどう感じるかな?」と考えられるようになります。
② 登場人物や作者の気持ちを想像する
物語を読むと、主人公だけでなく周りの人の気持ちも考えるようになります。そうすると、「自分の視点」だけじゃなく、「他人の視点」にも立てるようになる。これがまさに“客観的に考える力”なんです!
③ いったん立ち止まって考える習慣がつく
本を読む時、すぐに反応したり決めつけたりせずに、内容をじっくり考えますよね。この「一歩引いて考える」習慣が、現実でも『冷静に物事を見られる力』につながります。
↓
まとめると、本を読むことは「他人の頭の中をのぞく練習」や「自分の考えを整理するトレーニング」みたいなものです



ここの章の最初に出た、清水寺の見方もこれに当てはまりますね。1つの建物でも地理•歴史•観光といった様々な視点から観ることができるようになります。
知識が増え、選択肢が増える
読書で多くの知識を得ることができるので、知識が多いほど、より良い判断ができるようになります。



僕も調理をする時、「どんな料理があるのか」料理のカテゴリーを増やすためによくレシピ本を頼ります。
レシピ本を見ると「こんな料理があるのか」となりますし、「あ、これ作ってみたい!」て調理への意欲にも繋がりますしね。
また、例えば料理をするときに1種類の材料しか知らない人と、たくさんのスパイスや調味料を知っている人では、作れる料理の幅が違いますよね。
これは人生の選択にも当てはまって、読書を通じてたくさんの知識を得ることで、最適な選択ができるようになります。
つまり、読書は「他人の経験を疑似体験すること」 であり、それによって無駄な失敗を減らし、成功の可能性を高めることができます。



また、「このやり方がダメだったら、別の方法を試そう」と何かに挑戦する時にも選択肢が増えて、柔軟に考えられるようになるので、失敗を繰り返さず、成功に近づけます。
本を読めば案の発明家?!〜(12)アイデアが得られる〜


6章の「悩みや課題の解決するヒントが得られる」でも紹介しましたが、読書をすると新しい知識や視点が手に入るため、アイデアが得られやすくなります。
本には、著者の経験や考え方、また他の人が気づいたことがたくさん詰まっていますね。
自分ひとりで考えているだけでは思いつかないことも、本を通して知ることで、「あ、こういう考え方もあるんだ!」って気づくことができるんですね。
それに、本を読むと頭の中でイメージをふくらませることができるので、新しい発想が生まれやすくなります。
ビジネス書を読んで「こういう方法があるんだ」と知ったら、自分の中で応用してみて、「こうすともっと良くなる」といった新しいアイデアを生み出すこともできます。
また、読書は自分が得たいアイデアのジャンルの本を読むだけでなく、違うジャンルの知識を組み合わせるとさらにオリジナル性が高いアイデアが生まれやすくなります。
1. 哲学 × 物語 → 心に残る作品づくり
哲学書で「人間とは何か」「幸せとは何か」を考え、小説や漫画の物語から「感情の動き」を学ぶことで
→ 「深いテーマを持ったストーリー」や「考えさせられるキャラ設定」が生まれる。
2. 心理学 × 経営 → 人を動かすマーケティング
心理学の本で「人がどういう時に行動するか」を学び、経営やビジネスの本で「商品を売る仕組み」を知ることで
→ 「お客さんの心を動かす広告」や「買いたくなる売り方」が生まれる。
3.地理 × 食文化 → 観光や商品アイデア
地理の本で「その土地の気候や特産物」を知り、
料理本や文化本で「食べ方・習慣」を知ると、
→ 「ご当地グルメ」や「地域限定スイーツ」などの新しい企画を思いつける。
例:「抹茶 × チョコ」で京都らしいスイーツ、みたいな発想。
つまり、読書は「他の人の知識や考えを借りて、自分のアイデアを広げられる」と言えますね。
人として守るべき考えを身につけよう〜(13)論理的思考が身につく〜


読書をすると、読んでいくうちに「これって正しいのかな?」「人として間違っていないかな?」と考えられる時がありませんか?
例えば、小説で主人公のライバルが「勝つためなら他人の不幸は関係ない」と言う描写がある時ですね。そんな時に「それって人としてどうなの?」と考えるかなと思います。このように、文章を理解するために、頭の中で自然と論理の流れを整理するため、論理的思考が身につきます。



節約に関する本で、もし「お金の消費を減らすために、外食時は必ずおごってもらおう」とか書かれていたら、人に頼りっぱなしで「ん?それってどうなの?」て思いますよね
特に、ビジネス書や推理小説といった論理的に書かれた本は、因果関係や根拠をしっかり説明しているので、それを読み取ることで、自然と論理的な考え方が鍛えられます。
「犯人はなぜこの手口を使ったのか?」「探偵はどんな証拠をもとに推理しているのか?」と考えながら読むことになります。
そうすることで、筋道を立てて考える力が身についていきますよね。
また、論理的に書かれた文章を読むことで、「わかりやすい説明とはどういうものか?」がわかるようになります。
自分で考えを整理する時も、自然と分かりやすい説明になるように「まず結論を言って、それを支える理由を説明しよう」といった構成ができるようになります。
そのため、読書を続けることで、「筋道を立てて考える力」や「わかりやすく説明する力がどんどん鍛えられて、論理的思考が身についていいきます。
何事にも必要な注意する力をつける〜(14)集中力が鍛えられる〜


読書をすると、文章を理解するために意識を本に向け続ける必要がありますね。
本を読む時間は本に意識を集中するので、集中する力が鍛えられます。それを繰り返し続けることで集中力が上がります。



スマホやテレビのように次々と切り替わる情報と違って、本は自分で文字を追いながら内容を理解しないといけないです。
つまり、同時に2つの行動が必要なため、他のコンテンツよりも集中力が必要になり、集中力が上がりやすくなります。
特に、小説や論理的な本を読むときは、登場人物の関係や話の流れを覚えたり、筆者の主張を理解したりしながらページを進めるので、途中で気が散ると内容がわからなくなってしまいます。
そのため、自然と「今は本に集中しよう」という意識が働いて、集中力が鍛えられるようになります。
長時間読書をする習慣がつくと、少しのことで注意がそれにくくなり、勉強や仕事でも「一つのことに集中し続ける力」がついていきます。



逆に、普段スマホやSNSの短い情報にばかり慣れていると、長時間集中するのが難しくなりやすいです。
集中力が必要な読書は、集中力を鍛えるのにぴったりなトレーニングになります。
なので、最初は短時間でもいいので、毎日少しずつ読書を続けてみると、自然と集中力が伸びていきます。
本を読んで脳活〜(15)脳が活性化する〜


読書には「文字を読む」「内容を理解する」「内容を推測する」「内容に対し感情が起こる」など、たくさんの動作を行いますね。
それらの動作は、それぞれ違う脳の部位が働くことで起きるので、多くの脳の領域を同時に使うことになります。
「本を読む」という行動の中には様々な動作・脳の働きが行われますが、今回は5つに絞って紹介させて頂きますね
。
読書に関わる脳の部位
- 文字を認識する(後頭葉)
- 言葉の意味を理解する(側頭葉)
- 文脈を考え、推測する(前頭葉)
- 感情を動かす(側頭葉)
- 読んだ内容を覚える(側頭葉)
文字を認識する(後頭葉)
まず、目で文字を見て、文字の形•配置の視覚情報を処理するために後頭葉にある視覚野が働きます。
言葉の意味を理解する(側頭葉)
次に、読んだ言葉の意味を理解するために、側頭葉が活発に働きます。
たとえば、「リンゴ」と書いてあれば、過去の経験や知識と結びつけて、「赤くて丸い果物」とイメージしますよね。
この作業を繰り返すことで、言語の処理能力が向上します。
文脈を考え、推測する(前頭葉)
読書は単なる文字の認識だけじゃなく、「この登場人物はなぜこんな行動をしたんだろう?」や、「この文章の結論は何だろう?」と考える作業も必要になります。
これは前頭葉が担当しており、論理的思考や問題解決の能力を高めるのに役立ちます。
感情を動かす(側頭葉)
小説や感動的なエピソードを読むと、登場人物の気持ちに共感したり、自分の経験と重ね合わせたりしますよね。
このとき、気持ちを司る側頭葉にある大脳辺縁系の扁桃体が働いて、脳が活性化します。
読んだ内容を覚える(側頭葉)
小説を読んでいると、ストーリーや登場人物を覚えていきますよね。
読んだ本の内容を記憶するのは側頭葉の大脳辺縁系にある海馬が働いています。
こうした活動を続けることで、記憶力や創造力も鍛えられます。
読書は視覚・言語・論理・感情・想像といった、脳のいろんな部分を同時に刺激するため、脳全体が活性化します。
読書を習慣にすると、思考力や記憶力もどんどん伸びていくので、続けるのが大事ですね。
まとめ
「本を読む」という行動によって、これだけの効果が得られますが、普段から本を読んでいる僕も今回の記事を書いていて「あ、言われてみればそうだな」てなるものあり再発見する機会となりました。
普段から読書をされる方には「読書の効果」を新たな「気づき」の機会、初めて・久しぶりに読書をされる方には「知る」機会になる記事になっていたら嬉しいです。



最後に、読書によって得られることも大切ですが、読書を「楽しむ」事も大切なことの1つです!
得られる事ばかりを意識しすぎて読書が楽しめる時間になれていなかったら、時間がもったいなくなってしまいますしね。
今回のブログはいかがでしたか?少しでも読書に興味を持ってくださる方がいたら嬉しいです。
それでは、最後までお読みくださり、ありがとうございました。