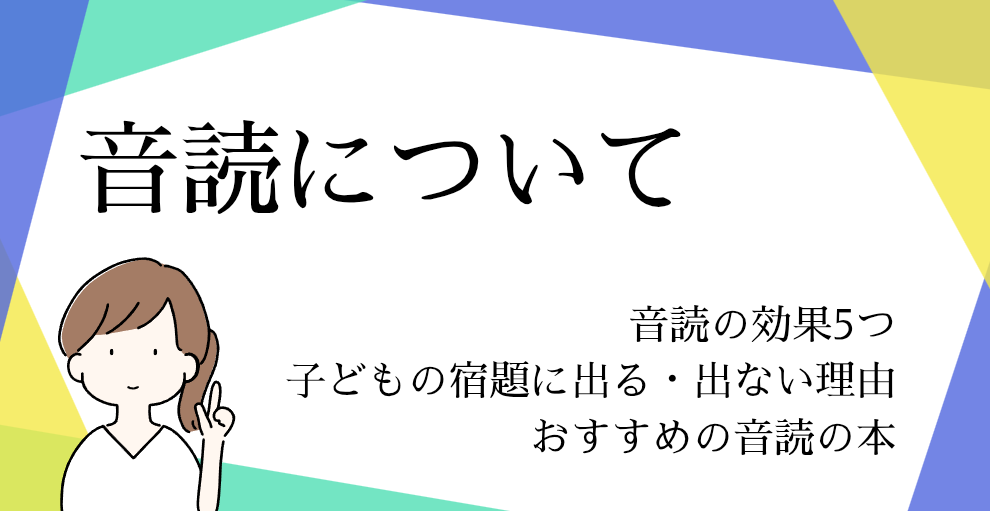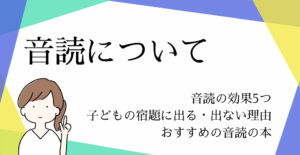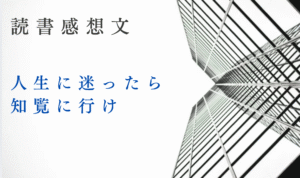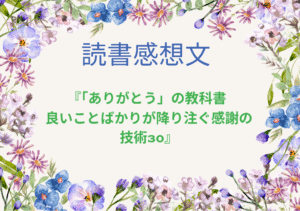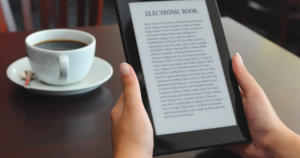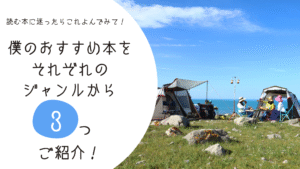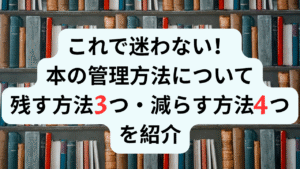よーさん
よーさんこんにちは、よーさんです。
今回は、何の話をしようかな



ねぇ、よーさんは音読ってやるの?



音読、もちろんあるよ
音読は小学校の頃宿題でよくやったし、今は自分の子どもに絵本を読んでるよ



そうなんだね。子どもの頃たくさんやったけど、音読って宿題で出るくらいだし何か意味があるのかな?



もちろんあるよ!
それじゃあ、今回は音読について触れていこうか。色々効果があるけど、1つずつ解説していこう
今回の記事でこれらのことが分かります
- そもそも音読とは
- 音読による効果つ
- なぜ子どもに音読がいいのか
音読の経験は誰でも経験あると思いますが、大人になるとなかなか音読できる場所も少なく、自宅とかでないと難しいですよね、
でも、音読には朗読よりも良いところもたくさんあり、それらを紹介していきますね。
読書習慣の参考になる話になる話ですので、ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。
音読について〜どんな特徴がある?〜
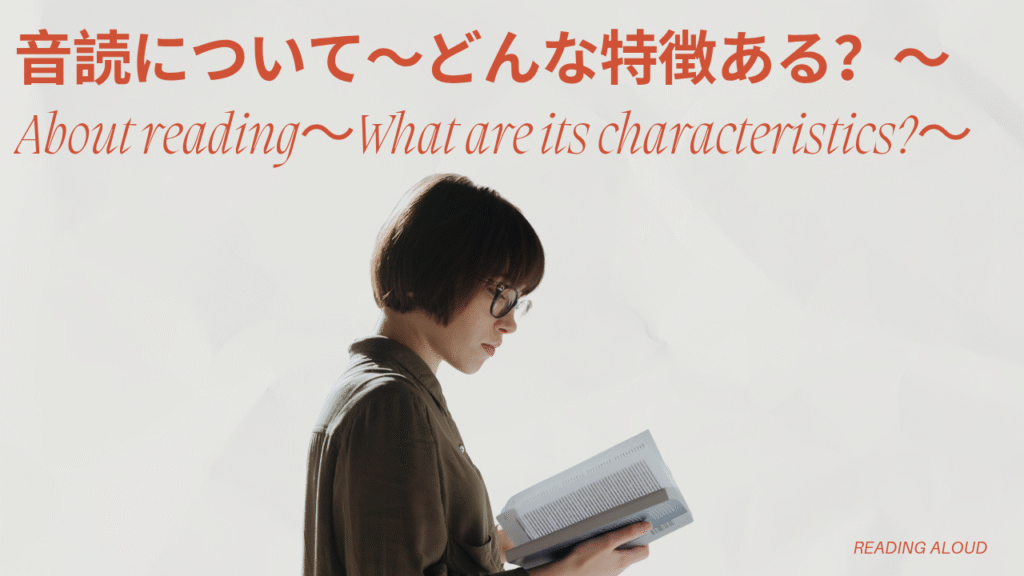
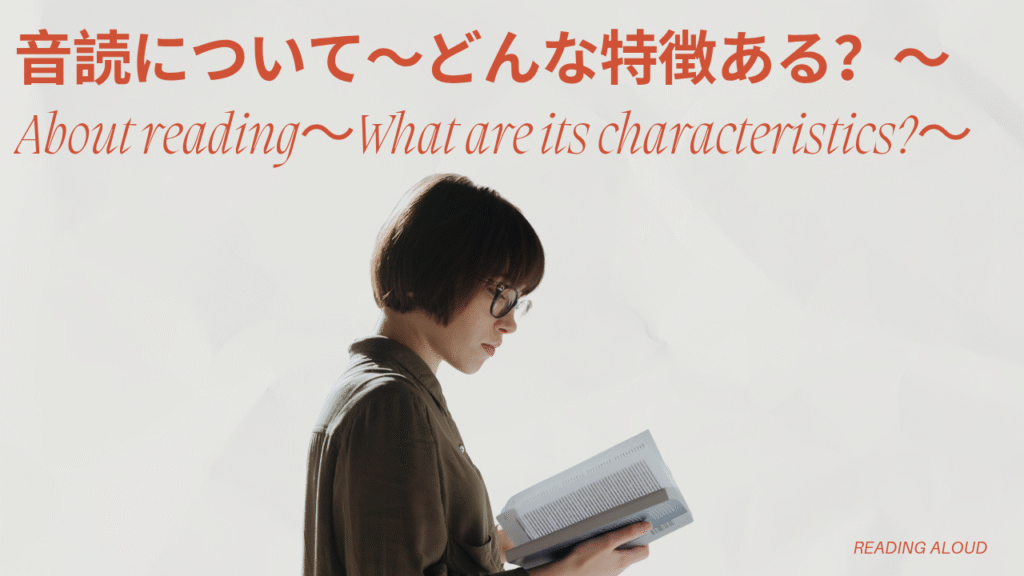
そもそも音読って何?音読と黙読の違い



それじゃあ、始めようか。
そもそも音読とは、皆が誰でも行ったことがあると思うけど、文章や本などを声に出して読むことを意味するよ。



声に出して読むのが音読だよね。
じゃあ、普段みんなが行っている声を出さない文字を読む読書は何ていうの?



普段みんなが行う読書(声を出さないで心の中で文字を読む方法)は黙読というよ。
音読の5つの効果



音読と黙読。
音読はどんな効果があるの?



主に5つの効果があるよ。ポイントとしてリストで伝えるね
音読の効果5つ
- 記憶に残りやすい
声に出すことで「目・脳・口・耳」を使うので、記憶に残りやすくなります。「目で文字を見て、脳で文字を認識して、口で声に出すことで、声を耳が聞く」と、視覚情報と言語情報と2つの情報を得られるようになります。 - 集中力がアップする!
声に出して読むと、書いてある文字をしっかり見て、集中していないと読めないので、集中しやすくなります。 - 理解力が深まる!
上の「記憶に残りやすい」でも書いた、「文字」と「声」で2つの情報が入ってくる。あと、「ヒュー」で風の音を出すシーンがあったら実際の音に似せて伝えようとか想像して工夫して読むと理解も深まります。 - 読む力・話す力がつく!
読む練習になるだけじゃなく、発音や話すリズムの練習にもなります。よく早口になりやすい人で「よく聞こえない」て言われたら「あ、この速さだと速いんだ」と気付いて話し方を直す機会にもなれますね。 - 言葉に慣れる!
新しい漢字や言葉に何度もふれることで、自然と語彙力(ごいりょく)がアップします!



こんなにたくさんあるのね。



そうだね。絵本を読んでいて本当感じるけど、音読では情報量も多くなるから一度読んで内容を覚えられる量も全然変わってくるね
僕の感覚だと、黙読だと一度で約半分内容を覚えるけど、音読だとセリフとかも含めてほとんど覚えられたね



音読って大事なんだね。
だから、子どもの頃によく宿題で出てたのかな
子どもの宿題に音読が出る理由5つ





これは色んな大人の人から質問が出るね。
大きな理由は5つあるんだ
なんで子どもの頃に音読を行っていたのか
- 言葉の力を育てるため
音読することで、「読む力」だけじゃなく「話す力」や「聞く力」も一緒に育ちます。日本語のリズムや言葉の使い方に慣れることができます。 - 内容をしっかり理解するため
声に出して読むと、頭の中でもう一度整理することになるので、ただ目で読むよりも内容がよくわかるようになります。 - 記憶に残りやすくするため
目で見て、口で読んで、耳で聞く。こうやっていくつもの感覚を使うと、覚えやすくなります。 - 発音や読み方の練習になる
漢字の読み方や言い回し、正しいイントネーションを学ぶいい機会としても活用されていました。 - 自信をつけるため
毎日声に出して読むと、読むことに慣れていきだんだんスラスラ読めるようになっていきます。それが出来た事への自信にもつながります。



こういう事が目的だったんだね。
ただ内容がわかっていればいいだけなのかと思ってた。



内容の理解だけではなかったんだよね。
小学生や子供の頃は、まだまだ言語の発達が進むから、発声の練習としても大事なんだね。



知れてよかった。
あと、小学校でよく行っていた音読も中学生になると減っていくよね。
それはなんでなの?
中学生になると、だんだんと取り組まなくなる音読。回数が減っていく理由4つ





いい所に目をつけたね!
確かに、僕も中学生になると、どんだけの回数が減っていったね。
大きな理由としては、学ぶ目的や勉強のスタイルが少し変わってくるからだね。



学ぶ目的?



そう!学ぶ目的。
これも4つの理由があるよ
中学生以降、音読をする時が減っていく理由
- 学習の目的が「読む」から「考える・解く」にシフトするから
小学生までは、「正しく読めるか」「内容がわかるか」が中心でしたが、中学生になると、「文章の構造を分析する」「筆者の主張を読み取る」「記述問題に答える」など、より高度な読解や表現力が求められるようになります。 - 授業時間が足りなくなるから
中学校になると、英語・数学・理科・社会・国語など、教科がどんどん増えます。
この中で限られた授業時間をやりくりするには、音読よりも効率的に知識を教えられる方法が優先されがちになります。
たとえば、漢字テスト、文法ドリル、読解問題の演習などです。 - 思春期で「恥ずかしさ」や「人前での緊張」が強くなるから
これはけっこう大きな理由です。
中学生になると、周りの目を気にするようになりやすいですよね。
「声が変」「噛んだらどうしよう」「間違えたら笑われるかも」…って思って、音読に苦手意識を持つ子も増えます。
先生たちも、生徒の心理を考えて、全員での音読をあまり強制しなくなることがあります。 - 「読む力」はある程度身についたとみなされるから
小学校の音読は、「読む力の基礎づくり」が目的でしたよね。
なので中学校以降は、「もうその土台はできているはず」と考えて、次のステップ(=考える力、書く力)に進みます。 - 入試に「音読の力」が直接出ないから
高校入試や大学入試では、「音読できるか」は基本的に問われないです。
テストで点を取るには、「黙読で早く正確に読んで、答える力」が求められるから、先生たちも試験対策を優先してしまうことが多いです
まとめると…
中学生以降に音読の機会が減るのは、
勉強内容が高度化・多様化し、試験重視になり、さらに生徒の心理的な変化もあるためですね。
しかし、音読が無意味になったわけじゃなく、むしろ自分で勉強するときに音読を取り入れると、
・記憶しやすくなる
・集中しやすくなる
・読むスピードや表現力が上がる
など、大人になっても役立つ効果がたくさんあります!



音読する回数が減ってラッキーって思ってたら、こういう理由があったんだね。



そういうことだね。
でも、音読は子どもも大人でも大切なことだから、音読しないといけない時が減っても、自分でやっていくことは良いことだよ



じゃあさ、最後に音読にはどんな本がいいのか教えて!
音読に良い本


- 1. 言葉の美しさ・リズムを楽しみたいなら
『銀河鉄道の夜』宮沢賢治
幻想的な世界観と詩のような文章が特徴で、音読にぴったりです。少し難しい語彙もありますが、読むうちに引き込まれます。
『方丈記』鴨長明(現代語訳)
短めですが、静かな余韻と深い哲学があります。声に出すと独特のリズムが心地よいです。 - 2. 話し言葉・日常的な語りを練習したいなら
『星の王子さま』サン=テグジュペリ(日本語訳)
やさしい語り口で、声に出すととても気持ちいい作品。深いテーマも含まれています。
『小川未明童話集』
やさしく美しい日本語の使い方が多く、声に出して読むのにぴったりな童話です。 - 3. 心に響く日本語を味わいたいなら
谷川俊太郎の詩集
短くても深く、美しい言葉がたくさん。気分に合わせて音読できます。
『百人一首(現代語訳つき)』
一首一首に情景があって、声に出すと響きがとても綺麗です。和歌のリズムも楽しめます。 - 4. 初心者向けに音読しやすい短文が多い本
『声に出して読みたい日本語』齋藤孝
音読用に厳選された名文が載っていて、解説もあるのでとても使いやすいです。



こんなにたくさんあるんだね。
私も音読また始めてみようかな。



いいね!
あとは、短編集とかもいいよ。
短い話をいくつか入っている本なら物語が終わったら一区切りしやりやすいしね。
短編集でおすすめなら
- 1. ほっこり、やさしい世界観
『阪急電車』有川浩(2008年)
→ 各駅ごとに登場人物が変わる連作短編集。人のつながりや日常の奇跡みたいな出来事が描かれてて、心がほぐれます。テンポの良い会話が多くて音読にも◎。
『木曜日にはココアを』青山美智子(2019年)
→ 短い話が連なって少しずつつながっていくスタイル。読後感がとても明るく、声に出して読むとやさしさが広がりますよ。 - 2. クスッと笑えて軽やか
『鹿の王 水底の橋』上橋菜穂子(2019年)※番外短編集
→ 本編未読でもOKな短編が入ってます。日常の中にちょっとした冒険や笑いがあって、明るい気持ちになれる構成です。
『ひよっこ社労士のヒナコ』若竹千佐子(2022年)
→ 明るくて前向きな主人公が、失敗しながらもがんばる話。ゆるっとした語り口で読みやすく、音読すると元気が出ます。 - 3. ちょっと不思議、でも楽しい
『不思議の国のアリス気分』田丸雅智(2020年前後、ショートショート系)
→ 1話が数ページの超短編集。ちょっと奇妙でおもしろい話がいっぱいです。テンポも良くて声に出して読んだらクセになります! - 4. 大人も楽しめる児童書
『クレヨン王国』シリーズ(福永令三・再刊多数)
→ やさしい文章ですがしっかりした物語。クスッと笑えて、声に出して読むのが楽しい語り口です。
『ぼくのニセモノをつくるには』ヨシタケシンスケ(2014年)※絵本ですが大人にも人気
→ セリフ中心で読みやすく、明るい笑いが詰まってます。ちょっと疲れたときにもおすすめです。
まとめ





やはり、本の世界は色々なできることがあって楽しいね。
僕ももっと音読を楽しめそうだ!



最初は本を声に出して読むのは恥ずかしいけど、だんだんと慣れたら文のテンポを工夫して読めるようになるんだったよね



そうだよ!
静かなシーンでは〈声を小さく〉読んだり、車とか音が出る物が登場する時は本物に音を似せて声を出したりすると臨場感出ていいよね



聞く人は楽しくなりそうね



音読の読み方でどんどん聞く人も楽しくなっていくから、音読って奥が深いよね



私も、音読をやってみよう!



それでは、今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました!
また、次回の記事でお会いしましょう!